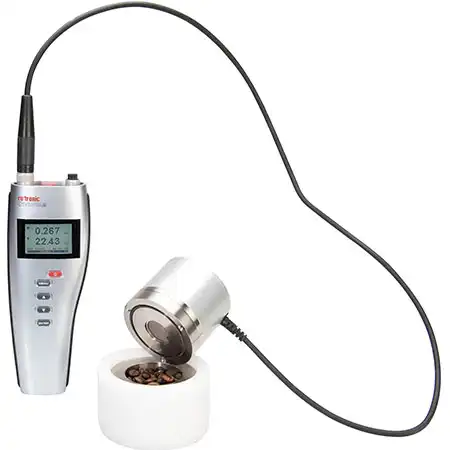COLUMN製品コラム
ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムとは?測定原理を徹底解説

分散液やナノ材料の研究・開発において欠かせないのが「ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム」です。ゼータ電位は粒子の表面電荷を反映し、分散の安定性を判断する重要な指標となります。また、粒子径や分子量を同時に評価することで、材料特性をより正確に把握することができます。
当記事では、この測定システムの基本的な仕組みや活用分野、ゼータ電位・粒子径・分子量を測定する代表的な原理について詳しく紹介します。
1. ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムとは
ゼータ電位とは、液体中に分散した粒子の表面と周囲の液体との間に生じる電位差のことです。粒子の分散安定性を左右する重要な指標であり、絶対値が大きいほど粒子同士の反発力が強まり、分散が安定します。一方でゼータ電位がゼロに近づくと凝集が起こりやすくなります。この特性を測定することで、分散液や懸濁液の安定性評価、配合設計の改善などに役立ちます。
測定にはレーザードップラー電気泳動法が用いられ、粒子の電気泳動速度をレーザー散乱で解析する仕組みです。ゼータ電位だけでなく粒子径や分子量も同時に測定可能な「ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム」が開発されています。このシステムにより、粒子の大きさ、分散状態、分子の質量などを一括で評価できるため、ナノ材料、医薬品、食品、化粧品など多様な分野で研究・開発を支える重要な分析技術となっています。
1-1. ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムの用途
ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムは、界面化学や無機物研究、ライフサイエンス、半導体、高分子、薬学、医学など幅広い分野で活用されています。特に新規機能性材料では、燃料電池関連のカーボンナノチューブやセルロースナノファイバー、DDSやリポソームなどのバイオナノ粒子の評価に役立ちます。セラミックスや顔料工業では、酸化チタンやカーボンブラックの分散・凝集制御、スラリーやカラーフィルターの改質研究に用いられます。
半導体分野ではシリコンウェハー表面の異物付着メカニズム解明やCMPスラリーの解析に応用され、高分子・化学工業ではエマルションやラテックスの機能性評価に寄与します。さらに医薬品・食品工業では、タンパク質や界面活性剤の特性評価に不可欠です。このようにゼータ電位測定は、分散安定性や凝集性、表面改質などを定量的に把握できる重要な手段として、多様な研究開発や品質管理を支えています。
2. ゼータ電位測定の原理
ゼータ電位を定量的に評価するためには、粒子や表面の電気的挙動を正確に観測する必要があります。そのために開発された代表的な手法が電気泳動光散乱法(ELS) と流動電位法です。前者は分散液中の粒子の動きを光学的に捉える方法であり、後者は固体表面と液体の相互作用を利用する方法です。ここでは、それぞれの原理と特徴を解説します。
■電気泳動光散乱法(ELS)
ゼータ電位の測定に最も広く用いられているのが電気泳動光散乱法(ELS)です。電気泳動光散乱法では、分散液に電場を印加し、粒子が持つ電荷の大きさに応じて移動する速度(電気泳動移動度)を測定します。強く帯電した粒子ほど速く移動し、その速度をレーザー光で照射すると、散乱光にドップラーシフトが生じます。この周波数変化を解析することで、電気泳動移動度が算出され、そこからゼータ電位が求められます。
従来の電気泳動光散乱法では、信号が小さいことや符号の判定が難しいという制約がありましたが、近年はPALS法やcmPALS法といった改良技術により、低電場での高感度・高再現性測定が可能になっています。また、動的光散乱法と組み合わせることで、粒子径と同時に評価できる点も特徴です。
■流動電位法
粉体やフィルム、繊維などのマクロサイズの表面に対しては流動電位法が用いられます。流動電位法では、試料を固定して毛細管流路を形成し、そこに電解液を流すと、液体の移動により固体表面の電気二重層がせん断され、イオンが移動します。これに伴って電荷分離が起こり、電圧差として観測されるのが流動電位です。得られた流動電位または流動電流の値を用いてゼータ電位を計算します。
基礎となる式はHelmholtzとSmoluchowskiにより導かれ、流路の長さや断面積、電解液の粘度・比誘電率などを組み合わせて算出されます。ただし、この式は平板試料に適しており、凹凸や不規則形状の試料には派生式を用いる必要があります。流動電位法は、コーティング膜や不織布など、液中で粒子が自由に動けない試料の評価に適している点が特徴です。
3. 粒子径測定の原理
粒子径の測定は、材料特性や分散安定性を理解する上で必要な要素です。特にナノメートルからマイクロメートルの領域では、光学的・物理的手法を駆使して精密な解析が行われています。代表的な方法には「動的光散乱法(光子相関法)」「遠心沈降法」「粒子軌跡解析法」があり、それぞれ異なる対象や特徴を持ちます。
■動的光散乱法(光子相関法)
動的光散乱法(DLS)は、溶液中で粒子が行うブラウン運動を利用して粒子径を算出する手法です。小さい粒子は速く、大きい粒子はゆっくりと動くため、その運動速度の違いを光の散乱強度のゆらぎとして観測します。得られた信号を時間相関関数で解析することで拡散係数を導き出し、ストークス・アインシュタイン式を用いて粒子径を算出します。ナノサイズの粒子測定に適しており、非侵襲的で迅速な評価が可能です。
■遠心沈降法
遠心沈降法は、粒子の沈降速度から粒子径を求める方法です。粒子は大きさや密度によって沈降速度が異なり、遠心力を利用することで高精度かつ短時間で分離・測定が可能になります。沈降速度はストークスの式に基づき、粒子径、密度差、溶媒粘度と関連付けられます。光学的検出器で透過光や吸光度をモニターすることで沈降挙動を追跡し、粒度分布を求めることができます。比較的大きな粒子や高濃度サンプルに適しており、材料工学やセラミックス分野で広く利用されています。
■粒子軌跡解析法(PTA)
粒子軌跡解析法は、顕微鏡とカメラを用いて溶液中の粒子を直接観察し、そのランダムな軌跡を追跡する方法です。レーザー照射で観察された粒子を輝点として記録し、フレームごとの位置変化から平均二乗変位(MSD)を算出します。これにより拡散係数を求め、ストークス・アインシュタイン式を用いて粒子径を導出します。多数の粒子を同時に解析することで個数基準の粒度分布が得られ、特に異なる粒子群が混在するサンプルに強みを発揮します。
4. 分子量測定の原理
分子量の測定は、高分子やタンパク質、ナノ材料の研究・開発において欠かせない工程です。特に溶液中における分子の大きさや相互作用を正しく把握することで、機能性や安定性の評価につながります。代表的な手法として「動的光散乱法(DLS)」と「静的光散乱法(SLS)」があります。それぞれ同じ“光散乱”を利用しますが、測定対象や解析手法に違いがあります。
■動的光散乱法
動的光散乱法は、分子や微粒子が溶液中で行うブラウン運動を散乱光のゆらぎとして検出し、その拡散係数を算出します。得られた拡散係数から水和半径(分子が溶媒に包まれた状態での見かけの大きさ)を求め、経験的な関係式や標準試料との比較を用いて分子量を推定します。
動的光散乱法は測定が迅速でサンプルの前処理も少なく済むため、タンパク質の会合状態や高分子の分散安定性を評価する際に広く用いられています。ただし、得られる値は“水和径を基にした分子量”であるため、厳密な絶対分子量測定には限界があります。
■静的光散乱法
静的光散乱法は散乱光の“強度そのもの”を解析する手法です。溶液にレーザーを照射し、分子からの散乱光強度を濃度や散乱角度との関係から測定することで、重量平均分子量や分子形態(サイズ、凝集状態)を直接的に算出できます。特にZimmプロットなどの解析法を用いると、分子量だけでなく第二ビリアル係数(分子間相互作用の指標)も得られる点が大きな特徴です。
静的光散乱法は希薄溶液を対象に高精度な測定が可能であり、ポリマー研究やタンパク質の構造解析に有効です。ただし、高濃度試料や不均一分散系では光多重散乱の影響を受けやすく、測定条件の制御が重要となります。
ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムの導入・選定でお悩みならアズサイエンス
まとめ
ゼータ電位・粒子径・分子量測定システムは、分散液やナノ材料などの特性を総合的に解析できる重要な技術です。ゼータ電位は粒子表面と液体の間の電位差を示し、分散安定性や凝集傾向の評価に役立ちます。粒子径は、動的光散乱法によるブラウン運動解析、遠心沈降法による沈降速度測定、粒子軌跡解析法による個々の粒子追跡などで算出されます。分子量は、動的光散乱法で推定し、静的光散乱法で高精度に測定可能です。
医薬品、食品、化粧品、半導体など幅広い分野で研究開発や品質管理を支える基盤技術として活用されています。
関連コラム
関連する機器
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
 お見積りはこちらから
お見積りはこちらから
-
資料請求
 資料請求はこちらから
資料請求はこちらから
PAGE
TOP