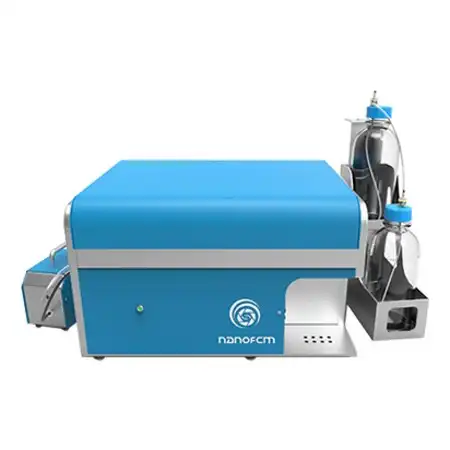COLUMN製品コラム
接触角計とは?静的接触角・動的接触角・粉体接触角の測定原理も解説

接触角計は、液体が固体表面へどの程度なじむか(濡れ性)を数値化するために用いられる測定装置です。材料の表面処理、コーティング品質評価、洗浄プロセスの管理など、多くの産業分野で欠かせない分析手法として広く利用されています。接触角は、液滴が固体表面に形成する角度を測定することで求められますが、その測定には静的接触角・動的接触角・粉体接触角など複数のアプローチがあります。
当記事では、θ/2法・Tangent法など代表的な測定原理から、動的測定や粉体評価まで、研究開発や品質管理で役立つ知識を体系的に解説します。
| 目次 1. 接触角計とは 1-1. 接触角とは 2. 静的接触角の測定原理 2-1. θ/2法 2-2. Tangent法 2-3. 真円フィッティング法・楕円フィッティング法 3. 動的接触角の測定原理 3-1. 傾斜法 3-2. 拡張/収縮法 4. 粉体接触角の測定 4-1. 浸透速度法 まとめ |
1. 接触角計とは
接触角計とは、固体表面に滴下した液滴を横方向から撮影し、その形状をもとに角度を計測するための装置です。旧来はファインダー越しに液滴を観察し、分度器で角度を読み取る目視型が主流でした。しかし、目視では読み取りのばらつきが大きく、特に液滴量が少ない場合は観察そのものが難しいという課題がありました。
現在では、CMOSカメラで液滴画像を取得し、専用ソフトが自動解析するデジタル型が一般的です。画像を拡大して表示できるため、複数人で同時に確認したり、データとして保存・共有したりすることが容易です。また、目視型より少量の液滴でも安定した測定が可能です。用途に応じて、動的測定に対応したタイプや、大型ワーク向けのモデルなども展開されています。
1-1. 接触角とは
接触角とは、固体表面に液滴を落としたとき、その液滴がどの程度広がるかを示す濡れ性(ぬれやすさ)の指標です。液滴を横から観察し、固体表面と液滴の接点における液滴輪郭の接線がつくる角度を測定して求めます。
液滴が大きく広がるほど接触角は小さくなり、固体に対して液体がよくなじむ「濡れやすい」状態を示します。一方で、液滴が球状に近いほど接触角は大きくなり、液体がはじかれる「ぬれにくい」状態と判断されます。
接触角は、固体と液体の表面張力や界面の相互作用によって決まり、材料表面の性質を評価する基本指標として多くの分野で利用されています。たとえば、表面処理の効果検証、コーティング品質の評価、洗浄工程のチェック、親水性・撥水性の比較など、工業・研究用途で非常に重要な役割を果たします。
2. 静的接触角の測定原理
静的接触角とは、液滴を固体表面に落とした後、液滴の形状が安定した「平衡状態」で測定する接触角のことです。液滴の左右端が動かず、輪郭が変化しない状態で評価するため、固体表面が液体をどの程度ぬらすかを定量的に把握できます。
表面の清浄度評価やコーティング品質の確認など幅広い用途で利用され、解析方法として「θ/2法」「Tangent法」「真円・楕円フィッティング法」などが用いられます。
2-1. θ/2法
θ/2法(Half-angle Method)は、静的接触角の測定で最も広く使われる解析手法です。この方法は、液滴が「球の一部」であると仮定し、液滴画像から左右端点と頂点を抽出して半角θ/2を求め、2倍して接触角θを算出します。
古くは液滴の高さhと半径rを測る計算式も利用されてきましたが、現在は画像解析により自動で判断されるのが一般的です。θ/2法は計算が簡単で処理が速く、重力の影響を受けにくい小さな液滴に適した方法として、多くの接触角計で標準的に採用されています。
2-2. Tangent法
Tangent法(接線法)は、液滴の端点付近の輪郭を「円弧の一部」とみなし、その円の接線角度から接触角を求める方法です。画像上で端点付近の点を複数抽出し、その点群から円の中心を算出して接線を導きます。この接線と固体表面との角度が接触角となり、左右それぞれ独立して測定できる点が特徴です。
θ/2法では液滴全体を球面と仮定するため左右の平均値が得られますが、Tangent法は左右で角度を分けて評価できるため、表面状態のムラや液滴形状が非対称な場合に特に有効です。より精密に界面状態を把握したい測定で用いられる信頼性の高い手法です。
2-3. 真円フィッティング法・楕円フィッティング法
真円フィッティング法は、液滴の輪郭を「真円の一部」と仮定し、取得した多数の輪郭座標に最小二乗法で円を当てはめ、その円の端点における接線角度から接触角を求める手法です。Tangent法より多くの座標を利用するため、ばらつきが小さく安定した値が得られる点が特徴です。
一方、実際の液滴は重力などの影響で理想的な真円からわずかに潰れることがあり、この誤差を補正するために用いられるのが楕円フィッティング法です。輪郭を楕円として近似し、端点の微分係数から接触角を算出します。真円では説明できない形状変化を精度よく反映できる一方、パラメータが増えるため計算はやや不安定になります。
輪郭形状が真円に近い場合は真円フィッティング、変形が大きい場合は楕円フィッティングを用いるなど、試料や液滴の状態に応じて手法を選択することが重要です。
3. 動的接触角の測定原理
動的接触角とは、液滴の形状や位置が変化している状態で測定する接触角のことです。液滴が前進する側の角度を前進接触角、後退する側の角度を後退接触角と呼び、付着性・滑落性の評価に用いられます。静的接触角では分からない「液滴の動きやすさ」を数値化でき、ガラス・タイル・コーティング材などの性能評価に有効です。
ここからは、代表的な測定手法である傾斜法と拡張/収縮法について紹介します。
3-1. 傾斜法
傾斜法は、水平な固体表面に液滴を載せ、その後ゆっくりと試料台を傾けながら液滴の挙動を観察する動的接触角の測定手法です。傾斜角が増すにつれて液滴は変形し、ある角度に達すると滑り始めます。この滑り出しの角度を滑落角といい、液滴が前進する側の接触角を前進接触角、後退する側の接触角を後退接触角と呼びます。これらの値は、表面に対する液滴の付着性や滑落しやすさの評価に役立ちます。
傾斜法では、前進接触角・後退接触角・滑落角に加え、液滴の直径や滑落速度などのデータも取得できます。一般的には、接触角計に傾斜ユニットを組み合わせて測定を行います。
3-2. 拡張/収縮法
拡張/収縮法は、固体表面に載せた液滴へ液体を追加したり、一方で吸い上げたりして液滴の形状を変化させ、そのときの接触角を測定する動的接触角の手法です。液滴は着液後しばらくすると静的な平衡状態になりますが、そこから液を注入すると液滴は膨張し、端部が前進する際の角度が前進接触角となります。
一方で液を吸入して液滴が縮む際、端部が後退するときの角度が後退接触角です。これらの差(前進角-後退角)は濡れのヒステリシスと呼ばれ、固体表面の粗さや化学的不均一性を評価する指標になります。測定は接触角計にオートディスペンサーを組み合わせて行われます。
4. 粉体接触角の測定
粉体の濡れ性は固体表面とは異なり、液滴が広がるだけでなく粒子間に浸透する挙動も伴うため、通常の接触角計では正確な測定が困難です。特に親水性の粉体では液体が急速に吸い込まれ、接触角の形状が保てず再現性も低下します。このため粉体の濡れ性評価では、液体が粉体層へ浸み込む速さを測定する「浸透速度法(ウォッシュバーン法)」が一般的です。
ここでは、粉体接触角の代表的な測定手法について解説します。
4-1. 浸透速度法
浸透速度法は、粉体に液体が毛管現象で浸み込む速度を測定し、濡れ性を評価する方法です。液体の浸透高さと時間の関係はLucas–Washburnの式で表されます。
| h²/t=rσcosθ/2η h:液体の浸透高さ r:粉体層を構成する毛管(細孔)の有効半径 σ:液体の表面張力 θ:接触角 η:液体の粘度 t:時間 |
実際の測定では、粉体を詰めたカラムに液体を接触させ、時間ごとの重量変化を記録します。W²とtの直線関係から浸透速度を算出し、表面張力・粘度・毛管半径を用いて粉体の接触角を推定します。
接触角計の導入・選定でお悩みならアズサイエンス
まとめ
接触角計は、固体表面に置いた液滴の形状から濡れ性を数値化する装置であり、現在はCMOSカメラと画像解析を用いたデジタル型が主流です。接触角は液滴が固体となじむ度合いを示す指標で、静的接触角では平衡状態の角度を、動的接触角では液滴の前進・後退の動きによる濡れ挙動を評価します。
解析手法にはθ/2法、Tangent法、真円・楕円フィッティング法、傾斜法や拡張/収縮法などがあり、目的に応じて使い分けられます。粉体の場合は液滴が浸透してしまうため、毛管浸透の速度を利用する浸透速度法が一般的で、Lucas–Washburn式から接触角の推定が可能です。
関連コラム
関連する機器
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
 お見積りはこちらから
お見積りはこちらから
-
資料請求
 資料請求はこちらから
資料請求はこちらから
PAGE
TOP