COLUMN製品コラム
顕微分光膜厚計とは?特徴や原理・用途・主な仕様を丁寧に解説
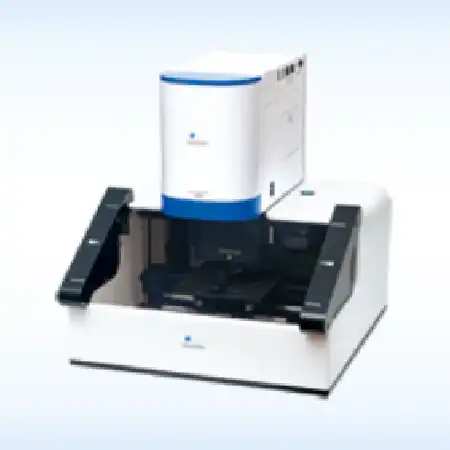
数マイクロメートル以下の領域における膜厚や光学特性の評価は、品質保証や研究開発に不可欠です。そうしたニーズに応える装置として注目されているのが「顕微分光膜厚計」です。
顕微分光膜厚計という名称は、一般的な呼称としても用いられていますが、大塚電子の製品名としても使用されています。大塚電子はさまざまな産業分野で利用される微小領域での高精度な膜厚・光学定数解析が可能な「顕微分光膜厚計 OPTM series」を販売中です。
この記事では、顕微分光膜厚計の動作原理、主要な特徴、装置を選択する際に考慮すべき主な仕様について詳しく解説します。
1. 顕微分光膜厚計とは?
顕微分光膜厚計は、分光法の原理と顕微鏡法を組み合わせることで、薄膜の厚さを測定し、屈折率(n)や消衰係数(k)といった光学特性を微小領域で分析する装置です。
顕微分光膜厚計の基本的な特徴は以下の通りです。
| 非接触・非破壊測定 試料に物理的な接触や損傷を与えることなく、膜厚を高精度に測定できます。 微小領域の測定 数マイクロメートル径の極めて小さな領域における膜厚測定が可能で、パターン化された薄膜や局所的な欠陥の解析に適しています。 高速測定 最新の装置では、1点あたり約1秒で測定できるため、高いスループットが要求される産業用途にも対応可能です。 光学定数の解析 膜厚に加え、屈折率や消衰係数の解析が可能で、材料の光学的挙動を理解する上で重要な情報を提供します。 広い波長範囲での動作 紫外(UV)から近赤外(NIR)までの広範な波長域に対応しており、スペクトル特性の異なる多様な薄膜材料や基板の測定が可能です。 |
1-1. 顕微分光膜厚計の原理
顕微分光膜厚計は、光の干渉現象を利用して、薄膜の厚さを高精度に測定する装置です。
顕微分光膜厚計の基本的な原理は以下の通りです。
| ・薄膜に光が照射されると、光の一部は膜の表面で反射し、残りは膜を透過して膜と基板の界面(あるいは多層膜の下層)で反射します。 ・これら複数の反射光波は互いに干渉し合い、光の強度に周期的な変化を生じさせます。(光波が同位相の場合は建設的干渉が起こり、反射光が強くなります。光波が逆位相の場合は破壊的干渉が生じ、反射光が弱くなります。) ・干渉の強さやパターンは、光が通る光路長の差によって決まり、これは膜の厚さおよび屈折率に依存しています。 ・装置は、白色光などの広い波長範囲の光を試料に照射し、反射された光を分光器で波長ごとに分解します。 ・分光器を通じて得られる反射スペクトルには、干渉による周期的なピークと谷が現れます。 ・スペクトルから干渉の極大・極小の波長を解析し、膜の光学定数(屈折率 n)が既知であれば、薄膜の厚さを正確に計算することができます。 |
2. 顕微分光膜厚計の用途・使用目的
続いて、顕微分光膜厚計の用途・使用目的について9つ紹介します。なお、ここで紹介する用途・使用目的は、大塚電子の「顕微分光膜厚計 OPTM series」を想定して取り上げています。
2-1. SiO2 SiNの膜厚測定
SiO₂(二酸化ケイ素)やSiN(窒化ケイ素)は、半導体デバイスにおける代表的な絶縁層材料です。SiO2やSiNの厚さを正確に測定することは、デバイスの性能制御や電流リークの防止において不可欠です。
特に、SiO₂は標準的な絶縁体として広く用いられ、SiNは高誘電率を有し、CMPストッパー層としても活用されます。
2-2. カラーレジストの膜厚測定
液晶ディスプレイのカラーフィルターは、RGB(赤、緑、青)のカラーレジストで構成されています。これらの膜厚が均一であることは、色再現性の確保やパターンの安定性に直結します。
膜厚にばらつきがあると、色むらや画質の低下を引き起こす原因となります。顕微分光膜厚計を用いれば、フィルター領域全体の膜厚均一性を非接触・非破壊で精密に確認できます。
2-3. ハードコートの膜厚測定
ハードコートは、耐摩耗性・耐衝撃性・耐熱性・耐薬品性などの特性を提供するために、高性能フィルムの表面に適用される保護層です。ハードコート層の厚さを制御することは、機能の確保とフィルムの反りなどの問題の防止において重要です。
膜厚が不十分であれば保護性能が損なわれる可能性があり、反対に過剰であれば不要な機械的影響を引き起こす恐れがあります。
2-4. ITOの構造解析
ITO(酸化インジウムスズ)は、透明導電膜としてディスプレイやタッチパネルに広く用いられています。ITOの光学的・電気的特性は、特にアニール処理後、膜厚や内部組成の変化に応じて変動します。
顕微分光膜厚計では、勾配モデルを用いた解析により、異なる深さにおける光学定数の変化を捉えることが可能です。これにより、ITO膜の組成変化を構造的に評価し、デバイス性能の最適化に活用できます。
2-5. 表面粗さを考慮した膜厚測定
試料の表面に微細な粗さがある場合、膜厚測定の精度に影響を与えることがあります。
顕微分光膜厚計では、このような表面粗さを「空気」と「膜材料」が1:1の比率で混合された「粗さ層」としてモデル化することで、より正確な膜厚値を取得できます。数ナノメートル単位の表面粗さを有するSiN(窒化シリコン)などの材料に対して有効であり、粗さを含めた光学モデルによって、下層の実膜厚を高精度に解析できます。
2-6. 干渉フィルターの測定
干渉フィルターは、特定の波長域において光を選択的に透過または反射するよう設計された光学部品です。異なる屈折率を持つ材料の多層膜構造で構成されています。
特に高精度なフィルターでは、高屈折率層と低屈折率層を一組として複数回繰り返し成膜されることがあります。
顕微分光膜厚計では、これらの構造に対して「超格子モデル」を用いた解析を行うことで、各層の膜厚や光学定数(n、k)を精密に測定できます。これにより、フィルターが設計通りのスペクトル特性を満たしているかどうかを非破壊で確認することが可能です。
2-7. 封止済み有機EL材料の測定
有機EL(OLED)材料は、酸素や水分に非常に敏感であり、通常は成膜後すぐにガラスで封止されます。
顕微分光膜厚計では、ガラスおよび中間の空気層を「非干渉層モデル」としてモデル化することにより、封止された状態のまま、ガラス越しに有機EL層の膜厚を非破壊で測定することが可能です。封止後の実デバイスを直接測定できるため、製品開発や品質管理の現場で有効に活用されています。
2-8. nk未知の極薄膜の測定
極薄膜(例えば厚さ100nm未満)では、膜厚(d)と光学定数(屈折率nおよび消衰係数k)の両方を同時に高精度で求めることが難しい場合があります。
このようなケースでは、「複数点同一解析」と呼ばれる手法が用いられます。複数点同一解析は、同じ材料で厚さが異なる複数のサンプルを測定し、nkが同一であると仮定して同時に解析する方法です。これにより、nkの精度が向上し、正確な膜厚値(d)を導出することが可能になります。
2-9. DLCコーティング厚みの測定
DLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングは、高硬度・低摩擦係数・耐摩耗性・高バリア性といった特性を持ち、工具・車載部品・医療デバイスなど幅広い用途で活用されています。
従来、DLC膜の膜厚測定には電子顕微鏡を用いた破壊検査が一般的でしたが、顕微分光膜厚計では、非破壊かつ高速での測定が可能です。また、波長範囲を調整することで極薄膜から超厚膜まで対応できるほか、形状のある実サンプルに直接測定が可能な光学系や、傾斜・回転ステージにも対応しています。
3. 顕微分光膜厚計の主な仕様
顕微分光膜厚計の主な仕様は、以下の通りです。
| 波長範囲 OPTM-A1:230~800nm OPTM-A2:360~1,100nm OPTM-A3:900~1,600nm 膜厚範囲 OPTM-A1:1nm~35μm OPTM-A2:7nm~49μm OPTM-A3:16nm~92μm サンプルサイズ 最大200×200×17mm スポット径 φ5・φ10・φ20・φ40µm |
(出典:大塚電子「顕微分光膜厚計 OPTM series」/
https://www.otsukael.jp/product/detail/productid/111)
顕微分光膜厚計の導入・選定でお悩みならアズサイエンス
まとめ
顕微分光膜厚計は、顕微鏡と分光光度計の機能を組み合わせた装置の総称であり、微小領域における薄膜の光学特性を非接触で測定・解析するために用いられます。
中でも、大塚電子が提供する「顕微分光膜厚計 OPTMシリーズ」は、ナノメートルオーダーの高精度な薄膜測定をはじめ、高速測定、多層膜の解析、光学定数(n・k)の評価といった高度な機能を備えた代表的製品です。研究開発から生産現場に至るまで、幅広い分野で利用されています。
関連コラム
関連する機器
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
 お見積りはこちらから
お見積りはこちらから
-
資料請求
 資料請求はこちらから
資料請求はこちらから
PAGE
TOP




