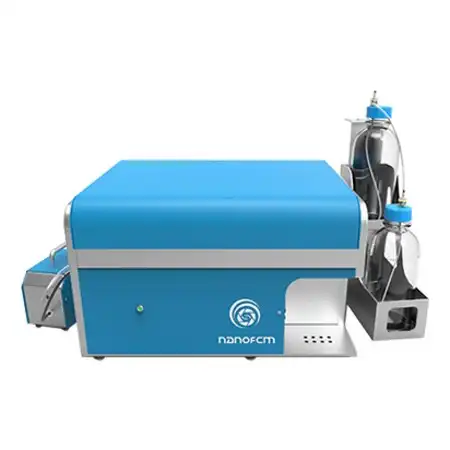COLUMN製品コラム
量子効率測定システムとは?原理や用途・主要なメーカーについて解説

新しい発光材料や太陽電池、有機ELなどの開発に取り組む際、「効率をどのように正しく評価すればよいのか分からない」と悩む研究者や技術者は少なくありません。そこで重要となるのが、内部量子効率や外部量子効率を正確に測定する「量子効率測定システム(量子収率測定システム)」です。
当記事では、量子効率の基本概念や測定原理、測定に必要な機器、代表的なメーカーを解説します。これらを理解することで、材料特性の本質を正しく評価でき、研究開発の精度向上や新技術の創出へとつなげられるでしょう。
| 目次 1. 量子効率測定システムとは 1-1. 内部量子効率と外部量子効率 1-2. 量子効率測定の原理 1-3. 量子効率測定システムの用途 2. 量子効率測定に使用される機器 2-1. 積分球 2-2. 分光器 2-3. 校正光源 2-4. 励起光源 3. 量子効率測定システムの主な製造メーカー まとめ |
1. 量子効率測定システムとは
量子効率測定システム(量子収率測定システム)とは、材料やデバイスが光をどれだけ効率よく変換・利用しているかを定量的に評価するための装置です。たとえば、蛍光体や有機EL材料の発光効率を調べる場合は、吸収した光エネルギーに対して実際に発光として放出された割合を求めます。これを量子効率と呼び、内部量子効率や外部量子効率といった指標で示されます。
また、太陽電池や光センサの分野では、入射した光子のうち電流や電圧などの電気信号に変換された割合を測定することで性能を評価します。測定は粉末、溶液、薄膜、固体フィルムなど多様な試料に対応しており、材料研究やデバイス開発に欠かせない手法です。
1-1. 内部量子効率と外部量子効率
内部量子効率(IQE)とは、材料やデバイスに注入された電子と正孔が再結合して発光に至る割合を示す指標です。再結合しても必ず光が放出されるとは限らず、一部は熱として失われるため、IQEは発光層で生じた光子の効率を測る基準となります。
一方、外部量子効率(EQE)は、発光層で生成された光子のうち実際に外部へ取り出される光子の割合を示します。多くの光子はチップ内部で全反射や吸収によって閉じ込められてしまうため、EQEはIQEよりも低くなるのが一般的です。たとえば、有機ELやLEDでは、内部で高い効率を得ても外部に出せる光は限定的であり、設計や材料工夫による光取り出し効率の改善が重要視されています。
1-2. 量子効率測定の原理
量子効率測定は、物質が吸収した光に対してどの程度効率的に発光を行うかを評価する手法です。物質に紫外や可視光を照射すると電子が励起され、一部は基底状態に戻る際に光を放出します。これを蛍光またはりん光と呼び、発光効率は吸収した光子数に対する発光光子数の比で表されます。
測定ではまずリファレンスを用いて励起スペクトルの強度を確認し、その後サンプルを照射して吸収と発光スペクトルを取得します。得られたデータから、吸収光と発光光の積分強度を比較することで、内部量子効率や外部量子効率が算出されます。一般的な装置は励起光源、積分球、分光器で構成され、粉末・溶液・薄膜などの多様な試料に対応できるのが特徴です。
1-3. 量子効率測定システムの用途
量子効率測定システムは、発光材料やデバイスの性能評価に幅広く活用されています。LEDや有機EL用蛍光体の量子効率測定はもちろん、フィルム状試料の透過・反射蛍光評価やリモートフォスファー用途のサンプル測定にも対応します。
また、量子ドットや蛍光プローブ、生体関連物質、錯体化合物の解析にも利用され、材料研究から応用分野まで高い汎用性を持ちます。近年注目される熱活性化遅延蛍光(TADF)材料のような次世代有機EL発光材料や、色素増感型太陽電池の効率評価にも不可欠であり、光エレクトロニクス研究の基盤技術として重要な役割を果たしています。
2. 量子効率測定に使用される機器
量子効率測定では、励起光源や積分球、分光器などの専用機器を組み合わせて用います。これらの装置により、試料が吸収した光子数と放出した光子数を正確に測定し、信頼性の高い効率評価が可能となります。ここからは、それぞれの機器の役割と特徴について詳しく解説します。
2-1. 積分球
積分球は、内壁に高反射率で拡散性の高いコーティングを施した中空球体で、入射した光を多重反射させることで内部の光強度を均一化する光学部品です。発光材料やデバイスは配光特性を持つため、直接測定では方向によって結果が変わってしまいます。
しかし、積分球法を用いれば方向依存性の影響を排除し、全放射光量に比例した信頼性の高い測定が可能になります。内部で均一化された光は光ファイバを介して分光器へ導かれ、強度解析に利用されます。透過率や反射率の測定にも広く用いられ、散乱性の高い試料やレンズのような光学部材の評価に欠かせない装置です。
2-2. 分光器
分光器は、光を波長ごとに分け、その強度を測定する装置です。内部にはプリズムや回折格子などの分光素子があり、光ファイバから入射した光を紫外域・可視域・近赤外域へと分散させます。その後、各波長に対応する多素子ディテクタが光を受光し、強度データを取得します。
得られたデータをつなぎ合わせることで、横軸に波長、縦軸に強度を示すスペクトルが得られ、発光特性や吸収特性を可視化できます。微弱光から強光まで比例的に測定でき、発光材料やデバイスの評価、環境モニタリング、食品検査など、多様な用途に活用される分析機器です。
2-3. 校正光源
積分球や分光器は光強度のスペクトルを測定できますが、波長ごとに応答度が異なるため、そのままでは正確なフォトン数を算出することはできません。そこで基準となる分光放射束が既知の校正光源を用い、各波長に応答補正係数を与えることで、励起光や蛍光の分光放射束スペクトルを正確に測定できるようになります。
校正光源は紫外域・可視域・近赤外域に対応しており、測定システムの信頼性を確保するために不可欠な役割を果たしています。
2-4. 励起光源
励起光源は、サンプルに光を照射するための装置で、LEDやレーザーが主に用いられます。これらの光は試料に適切な形で照射され、サンプル内の電子を励起して発光を誘起します。
量子効率測定システムでは、励起光源から出力された光がライトガイドを通じて積分球内へ導かれ、設置されたサンプルに均一に照射されます。サンプルが励起光を吸収すると、吸収された光の一部は長波長側の発光として観測されます。このデータをリファレンス測定と比較することで、励起光の吸収量と発光量を定量化し、発光量子収率を算出できます。
3. 量子効率測定システムの主な製造メーカー
量子効率測定システムは、光学・分析機器分野で高い技術を有するメーカーによって開発・提供されています。ここでは代表的な3社を紹介します。
| ・大塚電子株式会社 1970年に設立され、大塚グループの一員として光学・計測分野で発展してきた企業です。粒子径測定機やマルチチャンネル分光光度計など、多彩な計測機器を開発しており、量子効率測定分野でも高精度な装置を提供しています。医療や化学、半導体分野まで幅広く応用される技術力を持つのが強みです。 ・日本分光株式会社(JASCO) 光分析機器と分離分析機器の開発に強みを持ち、半世紀以上にわたり分光技術を磨き上げてきた老舗メーカーです。光学素子の開発から装置製造、アプリケーション研究に至るまで一貫した体制を構築しており、分析技術者向けのセミナー開催やアフターサービス網の充実によって研究現場を支えています。 ・浜松ホトニクス株式会社 「光を活かす技術」を企業理念とし、光センサから光源、さらにシステムまで幅広い製品群を展開しています。紫外線からX線領域まで対応する光デバイスは世界的に高く評価されており、量子効率測定システムにもその高感度センサ技術が活用されています。ライフサイエンスから宇宙観測、医療機器まで、幅広い分野に応用されている点が特徴です |
量子効率測定システムの導入・選定でお悩みならアズサイエンス
まとめ
量子効率測定システムは、材料やデバイスが光をどの程度効率的に変換・利用できているかを評価するための手段です。内部量子効率と外部量子効率の違いや測定原理、使用される機器の役割を理解することで、測定結果の信頼性を高められます。
各メーカーが提供する装置は、研究から産業まで幅広い分野で活用されており、それぞれが高い技術力と独自の強みを持っています。新素材開発や太陽電池、有機ELなどの高効率化研究に直結するため、光学特性の正確な評価は不可欠です。
関連コラム
関連する機器
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
 お見積りはこちらから
お見積りはこちらから
-
資料請求
 資料請求はこちらから
資料請求はこちらから
PAGE
TOP