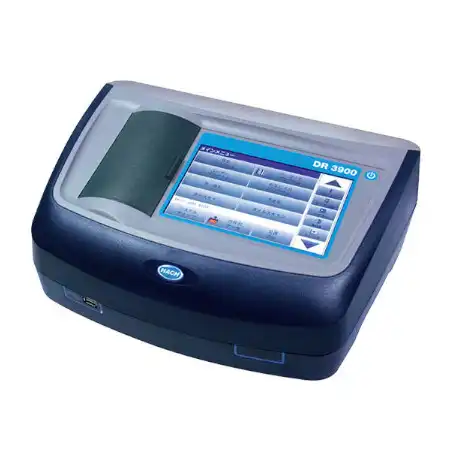COLUMN製品コラム
風速計とは?種類別の原理や主な用途・選び方を分かりやすく解説

風速計は、文字通り風の速さを測定する機器であり、気象観測にとどまらず、産業分野においても欠かせない機器です。例えば、建設現場におけるクレーン作業の安全性確保、風力発電における発電効率の最適化、空調設備の性能評価、工場やクリーンルームにおける環境管理などに使用されています。
この記事では、風速計の基本的な原理から、風速計の種類、それぞれの主な用途や選び方まで詳しく解説します。風速計について詳しく知りたい方や、風速計の購入を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
| 目次 1. 風速計とは 1-1. 風速計の主な用途 2. 【種類別】風速計の原理と特徴 2-1. 風杯型風速計 2-2. ベーン式風速計(風車型風速計) 2-3. 熱式風速計 2-4. 超音波式風速計 2-5. ピトー管風速計 2-6. 風向風速計 3. 風速計の選び方 まとめ |
1. 風速計とは
風速計は、文字通り風の速さを測定する機器です。風の強さは、人の生活や社会活動に大きな影響を与えるため、さまざまな場所で風速計が活用されています。風速の単位はメートル毎秒(m/s)やノットなどです。
風速計にはさまざまな種類があり、測定する場所や目的によって使い分けられています。
1-1. 風速計の主な用途
風速計の主な用途は、以下の通りです。
| 気象観測 気象観測では、天気予報の精度を高めるために風速計が使用されます。 交通機関 鉄道では、強風時の列車の速度制限や運休の判断基準として活用され、安全な運行を支えています。航空分野でも、離着陸時の風速や風向きの確認に用いられます。 建設現場 建設現場では、高所作業やクレーン作業などの安全管理に風速計が使用され、作業の中止判断などに役立てられています。 スポーツ分野 例えば陸上競技では、追い風の影響を判断するために使用されます。その他、ヨットレースやウィンドサーフィンなどの風を利用するスポーツにおいても、風速計は重要な情報源です。 |
2. 【種類別】風速計の原理と特徴
風速計は、測定原理や特徴によってさまざまな種類に分けられます。そのため風速計を購入する際は、それぞれの風速計の特徴を把握した上で、自社にとって適切な種類を選びましょう。以下では、代表的な風速計の原理と特徴を詳しく解説します。
2-1. 風杯型風速計
風杯型風速計は、半球状のカップ(風杯)を3個、水平な回転軸に取り付けた構造をしている風速計です。風が吹くとカップが風を受けて回転して、風を受ける面と受けない面で圧力差が生じ、回転力が発生します。回転速度が風速に比例するため、回転数を計測することで風速を測定できる仕組みです。
| 風杯型風速計の主な特徴 |
|---|
| ・風向の影響を受けにくく、どの方向からの風でも測定できる ・気象観測や一般の風速測定など、比較的広い範囲の風速を測定できる ・応答速度がやや遅く、急な風速の変化には追従しにくい場合がある ・風杯が風を受けるため、風の乱れの影響を受けやすい傾向がある ・構造が比較的単純で、安価に製造できる |
2-2. ベーン式風速計(風車型風速計)
ベーン式風速計は、風車のような羽根(ベーン)が風を受けて回転する構造の風速計です。羽根の回転速度が風速に比例するため、回転数を計測することで風速を測定します。
| ベーン式風速計の主な特徴 |
|---|
| ・屋内外を問わず使用可能で、温度変化の影響を受けにくいため、屋外での使用にも適している ・ビル管理法、健康増進法、事務所衛生基準規則などで定められた測定項目に対応している機種が多く、屋内環境測定にも活用できる ・小型・軽量なハンディタイプが豊富で、持ち運びや現場での測定に適している ・風速が急激に変化するような状況では、応答が遅れる場合があるため、比較的安定した風速を測定するのに向く ・風向に影響を受けるため、風向が大きく変化する場所では測定誤差が生じる可能性がある |
2-3. 熱式風速計
熱式風速計は、発熱体の冷却度合いを利用して風速を測定する機器です。
発熱体に電流を流して加熱し、そこに風を当てます。風が当たると発熱体から熱が奪われ、温度が変化するのでその温度変化(具体的には電気抵抗の変化)を測定し、風速に換算します。風速が速いほど冷却効果が大きくなり、電気抵抗の変化も大きくなる仕組みです。
| 熱式風速計の主な特徴 |
|---|
| ・微風速の測定に優れており、微弱な空気の流れも高精度に捉えられる ・センサー部分が小さいため、空調ダクト内やクリーンルームなど、狭い場所や入り組んだ場所での測定に適している ・発熱体の温度変化を利用するため、周囲の温度変化の影響を受けやすく、急激な温度変化の少ない屋内での測定に適している ・風速だけでなく、風温・湿度・圧力などを同時に測定できる機種もある |
2-4. 超音波式風速計
超音波式風速計は、音波の伝播を利用して風速を測定する機器です。
複数の超音波発信器と受信器を配置し、発信器から発信された超音波が受信器に到達するまでの時間を測定します。風が吹いていると、音波の伝播速度が風の影響を受け、到達時間に差が生じます。時間差を測定することで、風速と風向を算出する仕組みです。
特に、3次元超音波風速計は、複数の方向から超音波を照射し、水平方向だけでなく垂直方向(吹き上げ・吹き下ろし)の風速も測定できます。
| 超音波式風速計の主な特徴 |
|---|
| ・機械的な可動部分がないため、摩耗や故障のリスクが少なく、メンテナンス頻度を大幅に低減できる ・強風や悪天候などの厳しい環境下でも安定した測定ができる ・熱式風速計と同様、微風速の測定に優れており、非常に弱い風でも正確に捉えられる ・風速の変化に対する応答が速いので、瞬間的な風速の変化も捉えられる ・クリーンルーム内の気流管理、精密機器製造ラインの環境モニタリング、ビル風対策や高精度な気象観測、大気汚染拡散観測など、高度な分析が求められる分野で使用される |
2-5. ピトー管風速計
ピトー管風速計は、流体(気体や液体)の速度を測定する装置で、ピトー管は、流体の流れに対して正面と直角方向に小さな孔を持つ管で構成されています。
正面の孔から取り込まれる圧力は「全圧」、直角方向から取り込まれる圧力は「静圧」と呼ばれます。これらの圧力差を測定することで、ベルヌーイの定理に基づいて流速を算出します。
| ピトー管風速計の主な特徴 |
|---|
| ・比較的速い流速(一般的には5m/s以上)の測定に適している ・低速流では圧力差が小さくなり、測定精度が低下する傾向がある ・正確な測定のためには、ピトー管を流体の流れに対して正確に正面に向ける必要がある ・構造が比較的単純で、他の方式の風速計に比べて安価に製造できる ・高速流の測定、高温・汚染環境での使用、航空機の速度計測といった特定の用途に適している |
2-6. 風向風速計
風向風速計は、風の速さ(風速)と風の向き(風向)を同時に測定できる計測器です。最大の特徴は、風速と風向を一台で同時に測定できることです。
風向風速計には、風車型(プロペラ式)と超音波型の2種類があります。
風車型(プロペラ式)では、プロペラで風速を、垂直尾翼で風向を測定する仕組みです。垂直尾翼は風向きに合わせて回転し、プロペラの回転速度が風速に比例します。
超音波式は超音波の伝播時間を利用して風速と風向を測定する仕組みです。複数の超音波発信器と受信器を配置し、風による音波の伝播速度の変化から風速と風向を算出します。
| 風向風速計の主な特徴 |
|---|
| ・データロガーと組み合わせて使用することで、長期間にわたる風速・風向データを記録できる ・気象情報・交通機関・建設現場など、さまざまな場面で使用される |
3. 風速計の選び方
最後に、風速計を選ぶ際のポイントについて、3つの要素に分けて解説します。
| 屋内利用の場合 屋内では一般的に風速がそれほど強くないため、微風速を精度良く測定できる機種が適しています。具体的には、熱式風速計・ベーン式風速計・超音波式風速計などが挙げられます。 屋外利用の場合 雨・風・日光・温度変化などの厳しい環境に耐えられる耐久性・耐候性が必要です。防水性・防塵性・耐紫外線性などを考慮して選びましょう。ベーン式風速計・風杯型風速計・超音波式風速計・風向風速計などが挙げられます。 長期で測定する場合 気象観測、環境モニタリング、風力発電の風況調査など、長期間にわたってデータを収集する場合は、安定した電源供給が必要です。バッテリー駆動だけでなく、外部電源や太陽光発電などを利用できる機種もあります。 |
まとめ
風速計は、風の速さを測定する機器です。風速計の主な用途としては、気象観測における天気予報の精度向上や、台風や竜巻などの強風による災害予測、交通機関における安全な運行の確保、建設現場における高所作業の安全管理などが挙げられるでしょう。
また、風速計にはさまざまな種類があり、測定原理や特徴がそれぞれ異なります。代表的なものとして、風杯型風速計・ベーン式風速計・熱式風速計・超音波式風速計・ピトー管式風速計・風向風速計などがあります。
関連コラム
関連する機器
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
 お見積りはこちらから
お見積りはこちらから
-
資料請求
 資料請求はこちらから
資料請求はこちらから
PAGE
TOP